こんにちは、そーちゃんです。
今回は「日本のヘビを飼ってみたい!」「ヘビを捕まえたけどどうやって飼育するの?」といった方に、日本のヘビの代表格である、アオダイショウの特徴、捕まえ方から飼育方法までを徹底解説していきます!
アオダイショウの基本情報

アオダイショウは、日本に生息する「ナミヘビ科 ナメラ属」に分類されるヘビの一種で、ほぼ日本全土で確認されている、日本で最もメジャーなヘビとして知られています。
平地から山地にかけて幅広く分布しており、田んぼや民家で目撃されることも多く、食料を食い荒らすネズミを捕食対象にしていることから、かつては益獣としても扱われていました。
さらに、人里離れた場所にはあまり住んでおらず、公園や河川敷、神社などに生息していることから、現在も「人との関わりが深いヘビ」として人気を誇っています。
また、アオダイショウは成体で150cm~180cm程度、最大で”200㎝”ほどになる、日本でも最大クラスのヘビです。
成体になると、体色に青みが増してきて、さらに体も大きいことから「青大将」と名付けられたと言われています。

一方、アオダイショウの幼体は背中に斑紋があり、その姿は猛毒を持つヘビの「マムシ」によく似ています。これは、小さい幼体のときに、毒のあるマムシに擬態して天敵を怖がらせるためと考えられています。
寿命は、野生下で10年程度、飼育下においては15年程度と言われており、私たちが生まれてから、中学校を卒業するまで生きていると考えると、その寿命の長さが実感できるのではないでしょうか。
アオダイショウを捕まえたいなら田んぼへ行け!?
先程お伝えしたように、アオダイショウは公園や田畑、民家などの、人間が多くいるところにも生息しているため、他のヘビと比べると遭遇できる確率が高いヘビと言えるでしょう。
ただ、アオダイショウと遭遇する確率をより上げたいのであれば、個人的には5月~11月の間に田んぼに行くことをおすすめします!!!
田んぼにはアオダイショウの捕食対象である、カエルやねずみが豊富に生息している他、ヨシ原などに巣を作るオオヨシキリなどの巣の中にいる雛もアオダイショウの大好物のため、田んぼは彼らにとってごちそうの宝庫というわけです!!
では、実際に遭遇した際、どのように捕獲したらよいのでしょうか。
噛まれないためには頭を押さえろ!
アオダイショウに限らず、全てのヘビを捕まえる際は噛まれないために頭を押さえることを意識しましょう!
具体的にはこんな感じです。

こんな感じで頭を押さえることができれば、噛まれるリスクがなくなるため、写真のヤマカガシのような毒蛇でも容易に捕獲することができます!

ちなみに、アオダイショウには毒はありませんが、野生下では気の荒い性格をしている個体が多いため、捕まえる際には注意が必要です。
また、野生下のアオダイショウに噛まれると、感染症などにかかる危険性もあるため、なるべく噛まれないことをおすすめします。
私は何度か噛まれた経験がありますが、噛まれると結構痛いので要注意です(笑)
アオダイショウの飼育は難しい?

アオダイショウの飼育は特段難しいということはなく、同じナミヘビ科ということで、ヘビの飼育入門と言われるコーンスネークと同じような飼育環境を整えてあげれば、簡単に飼育を始めることができます。
しかし、飼育環境をちゃんと用意しないと、簡単に調子を崩してしまうので、まずはアオダイショウの飼育に必要な環境を知っておきましょう。
アオダイショウの飼育環境
飼育に必要なもの
・餌
・ケージ
・保温器具
・温湿度計
・床材
・水入れ
・シェルターや流木など
実は、上記のものさえ揃えれば、簡単にアオダイショウの飼育を始めることができるんです。
意外と簡単に始められそうですよね!!
では紹介していきます!!
餌
餌は、爬虫類ショップや通販で販売されている、冷凍マウスを与えましょう。
冷凍マウスのサイズはたくさん種類がありますが、目安としては飼育しているヘビの胴回りと同じくらいのサイズを与えてください。
餌のサイズが大きすぎると、そもそも食べてくれないことも多く、仮に食べれたとしても吐き戻しをしてしまい、拒食などの体調不良の原因となってしまいます。
逆に、餌のサイズが小さいと、食べるマウスの数が多くなってしまうため、シンプルに食費がかさんでしまうというデメリットがあります。
そのため、適切なサイズの餌を与えることが大事になってくるわけです。
今紹介した餌のサイズの基準は、ほとんど全てのヘビを飼育する際に当てはまるので是非覚えておきましょう。
冷凍マウスの通販はこちら!
ケージ
ケージの大きさは、飼育するヘビがとぐろを巻いた状態で6匹ほど入るほどの底面積のものが望ましいです。
ケージが大きすぎると、うまく脱皮することができなくなる危険性があり、小さすぎるとストレスを与えてしまう原因になってしまいます。
また、ケージは、毎日ヘビの様子が確認できるように、透明なアクリル素材のものかプラスチックケージがおすすめです。
おすすめのケージはこちら!
保温器具
アオダイショウの適温は25℃前後となっています。
ヘビは他の爬虫類と異なり、バスキングスポットなどは必要ないとされていますが、パネルヒーターなどを敷いて、ケージ内に温度差を作ってあげるとヘビにとって快適です。
おすすめのパネルヒーターはこちら!
温湿度計
アオダイショウの適温は25℃前後、適湿は40~50%となっています。
また、脱皮が近いときには霧吹きなどを使い、湿度を高め(60~70%)に設定する必要があり、この管理は温湿度計なしでは難しいです。
そのため、温湿度計は必ずケージに設置しましょう!
おすすめの温湿度計はこちら!
床材
アオダイショウの床材には、ヤシガラチップや水苔、ペットシーツなど、様々な種類が用いられていますが、個人的にはペットシーツがおすすめです。
ヤシガラチップや水苔は、保湿性やレイアウト性(見た目のおしゃれさ)に優れている一方、排泄物などでケージが汚れてしまった際の掃除が大変というデメリットがあります。
もちろん、こまめに掃除できる方であればヤシガラチップや水苔でも、ケージ内を清潔に保つことができますが、仕事で半日は家にいない方などは、見た目の悪さを差し引いてでも、ペットシーツを使った方がヘビにとっても、私たちにとっても快適な生活が送れます。
ちなみにヘビの排泄物はかなり強烈な臭いを放つとともに、液状で排泄されるため、適切な処理をしないと部屋中がとんでもない臭いになってしまうので、ご注意を…!!!
おすすめのペットシーツはこちら!
水入れ
アオダイショウは、田んぼや河川敷に頻繁に姿を現すことからも分かるとおり、水のある環境を好むヘビです。
そのため、飼育する際にはアオダイショウの身体がすっぽり入る程度の大きさの水入れを用意しましょう。
水入れは100均のタッパーなどで代用することができますので、自分が飼育するアオダイショウのサイズに合った水入れを用意してあげてください。
シェルターや流木など
このシェルターや流木をケージに設置する理由は大きく2つあります。
1つめはアオダイショウにとっての隠れ家になるため、飼育下におけるストレスが軽減されるから。
2つめは脱皮する際の手助けになるからです。
やはり、どんな生き物でも自分の姿が隠れるものがあると安心するので、シェルターや流木などを置いてあげることはとても重要です。
また、脱皮の際に脱皮殻が引っかかるようなオブジェクトがあれば、脱皮不全の予防にもなるのでケージに置いてあげましょう。
おすすめのシェルターはこちら!
日々のお世話は?

アオダイショウに限らず、ほとんどのヘビは毎日行うルーティンはほとんどありません。
毎日やることはといえば、水入れの掃除と取り替え、必要に応じて霧吹きくらいでしょうか。
また、排泄していた場合は床材の掃除をすぐにしてあげましょう。
では、その他はどうでしょうか。
餌やり
アオダイショウの餌やりの頻度は、幼体で3~4日に1回、成体で1~2週間に1回ほどといわれています。
ちなみに、私は上記の餌やり頻度の基準に加え、「排泄していたら与える」ということを意識しています。
排泄しているということは、次の消化を始める準備が完全に整ったという証拠ですので、この2つの基準を満たしたタイミングで与えるようにするのがおすすめです。
アオダイショウを初めとするヘビの仲間は、とてもエネルギー効率がよい身体をしているため、頻繁に餌を与える必要がありません。
むしろ、与えすぎてしまうと消化不良や吐き戻しの原因となってしまうため、餌の与えすぎにはくれぐれも注意しましょう。
脱皮の際の湿度管理
アオダイショウは脱皮する際に、普段よりも高い湿度を必要とします。
普段はケージ内の湿度を、40~50%ほどに保つところを、脱皮時には60~70%に上げなければなりません。
湿度を高く保たないと、脱皮不全のリスクが高まり、最悪の場合は身体の組織の壊死が起こってしまうので要注意です。
ちなみに脱皮のサインは、目が白くなることと、水入れの中に入る時間が長くなることです。

日々の観察の中で、このような様子があったら霧吹きなどで、湿度を高めにしてあげましょう。
まとめ

今回はアオダイショウの基本情報から捕まえ方、飼育方法までお話ししました。
アオダイショウは、日本人にとってとても馴染み深く、古来より愛されているヘビです。
ヘビは怖いイメージがあるかもしれませんが、一緒に過ごしてみるとその可愛さにメロメロになること間違いなしです!
皆さんが今年、素敵なアオダイショウを見つけられることを願っています。
見ていただきありがとうございました。
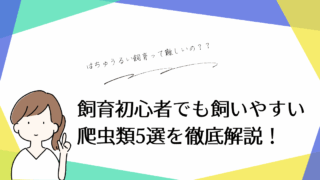











コメント